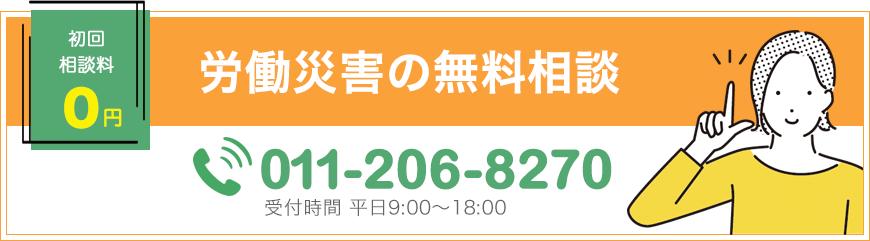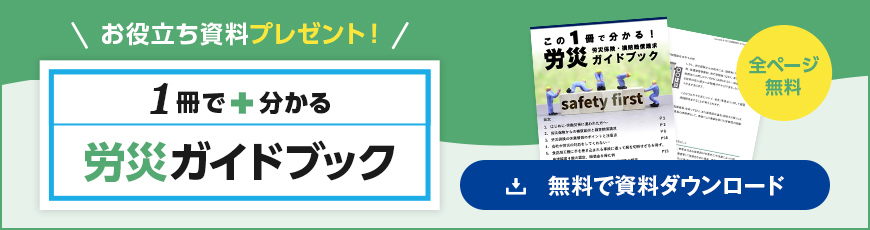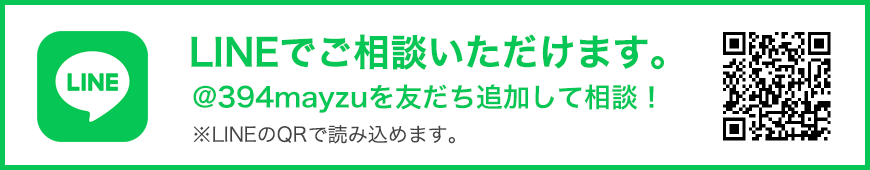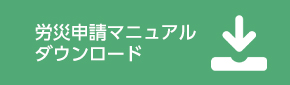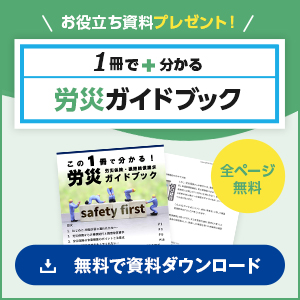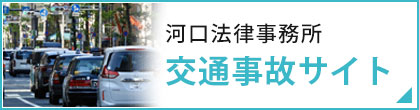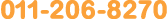労災における精神疾患、弁護士に相談すべき?
1 精神疾患も労災認定の対象
パワハラ・セクハラや過重労働などの業務上の原因からメンタル面を崩し、うつ病や適応障害などの精神疾患を発症してしまった場合や、業務上の大きな事故により身体的負傷のみならず、フラッシュバックするなど事故がトラウマとなって精神面も崩した場合などには、その精神疾患も労災保険の対象となり、労災保険から給付を受けられる可能性があります。
2 精神疾患についての労災認定要件と労災申請について
業務上の原因から精神疾患を発症したと労働基準監督署に認定されるには、労災認定要件を満たさなければなりません。
この点については、当サイトの「うつ病など精神疾患の方へ」の記事をご参照ください。
また、どのような点に気を付けて労働基準監督署への労災申請を行えばよいのかも、当サイトの「うつ病など精神疾患の方へ」の記事をご参照ください。
3 弁護士に相談するタイミング
(1)当事務所の提供サービス
当事務所では、精神疾患の労災申請自体を代理したり、サポートしたりするサービスは提供しておりません。
労災認定後に会社や加害者に対する損害賠償請求をすることについてのご相談やご依頼は承っております。
(2)相談のタイミングについて
当事務所では、ご相談は労災認定を得てからしていただくようお願いしております。
(3)損害賠償のタイミングについて
精神疾患について労災認定を得て、労災保険扱いの治療を受けられたとしても、会社や加害者に対する損害賠償請求をするタイミングは、治療が終わった後となります。
なぜなら、損害賠償としての慰謝料や休業損害などは、治療にどれほどの期間を要したのか、働けない期間がどれくらいだったのかによって、金額が変わるので、治療が終わってみなければ、そもそも損害賠償請求金額が定まらないからです。
そして残念ながら、精神疾患は治療が長引く傾向にあります。また、身体の怪我のように「これで治った」とわかりやすく判定(診断)できるわけでもありません。
また、治療の結果、精神疾患がすっかり治ればよいのですが、一定の症状が残ってしまった(後遺症状)ということもあり得ます。
そのような場合、症状固定(これ以上、根本的には良くならないという状態)の診断を得て、後遺症状について障害等級認定を得るべく労基署に障害申請をするという手続が必要となります。
障害等級の有無や何級と認定されるかによっても、損害賠償請求額は大きく変わってくるので、障害申請は非常に重要な手続です。
労災における精神疾患でお悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。