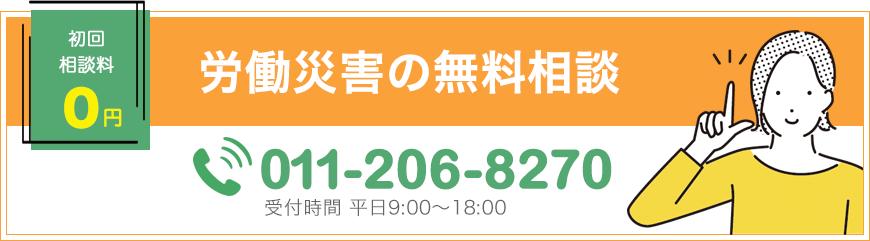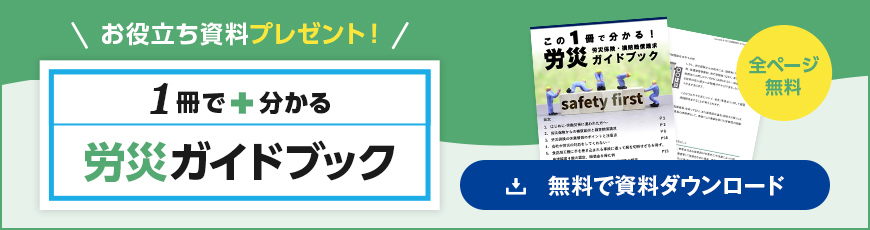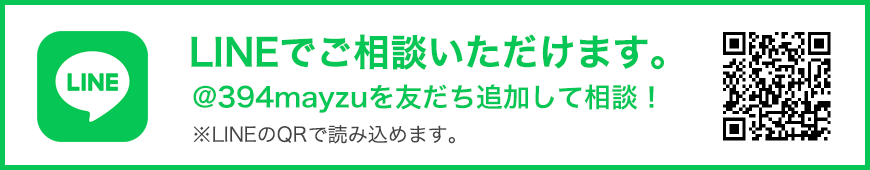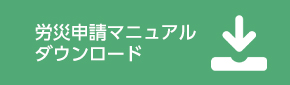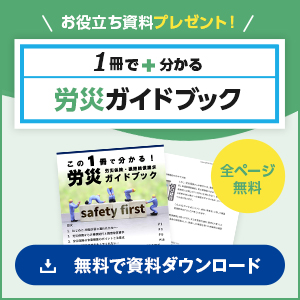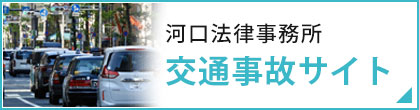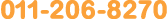仕事中に熱中症になったら労災として認められる?【弁護士が詳しく解説】
目次
・熱中症とは
・熱中症と労災 労災認定基準
・近年の熱中症労働災害の件数、熱中症予防のための法規制の強化
・熱中症の労災事故の実例
・労災による熱中症の損害賠償請求について
・早めの相談・依頼で安心を
熱中症とは
熱中症とは、体温が上がり、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能が働かくなったりして、体温の上昇やめまい、けいれん、頭痛などのさまざまな症状を起こす疾病をいいます。
屋外だけでなく屋内でも発症し、重症化すると命に関わることもあります。
特に近年は、止まらない地球温暖化の中、夏季の高温多湿の環境は非常に厳しく、本州はもちろん、それまで比較的涼しかった北海道でも熱中症は増加しています。
そのため、熱中症に対する十分な警戒と対策が必要とされています。
熱中症と労災 労災認定基準
特に夏季には、高温多湿な屋外環境で長時間にわたる業務に従事することは珍しくありません。屋内での作業でも厳しい高温多湿な環境もあります。
建設業や製造業が典型的ですが、運送業や警備業など様々な業種で熱中症の危険があります。
このように厳しい環境下での業務中(仕事中)に熱中症となってしまった場合、基本的には労災として認定されると考えて差し支えありません。
業務中の怪我や疾病が労災と認められるかどうかは、①業務遂行性、②業務起因性の2つの要件を満たすかどうかで判断されます。
①業務遂行性というのは、労働者が事業主の指揮命令下で業務を遂行中であったことを意味します。事業場内での業務や休憩時間はもちろん、出張や配達などの事業場外での業務であっても、業務遂行性は肯定されます。
②業務起因性というのは、怪我や疾病が業務によって引き起こされたものであることを意味します。高温多湿環境下での熱中症であれば、業務起因性も肯定されるのが通常です。
近年の熱中症労働災害の件数、熱中症予防のための法規制の強化
令和7年5月30日に厚生労働省から公表された令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)によると、令和6年(2024年)の職場における熱中症による死傷者は1257名(死亡者31名)であり、ここ数年間、どんどん増加している状況です。
令和6年(2024年)の死傷者1257名(死亡者31名)
令和5年(2023年)の死傷者1106名(死亡者31名)
令和4年(2022年)の死傷者 827名(死亡者30名)
令和3年(2021年)の死傷者 561名(死亡者20名)
そのため、国も熱中症災害の多発を踏まえて、死亡などの重大災害を予防するために、規制を強化しています。令和7年(2025年)6月1日から施行された労働安全衛生規則による規制であり、違反には罰則も設けられています。
これまでの法令規制では、熱中症関連については、塩及び飲料水を備えておくことの規制がありました(労働安全衛生規則617条)
(発汗作業に関する措置)
第617条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を 備えなければならない。
今般、新設された労働安全衛生規則612条の2では、熱中症のおそれのある環境での作業に労働者を従事させる場合には、熱中症と疑われる症状がみられた場合の報告体制の整備、その体制の周知義務が定められました。
また、熱中症と疑われる症状がみられた場合に採るべき処置(作業からの離脱、身体の冷却、病院受診)の手順を定め、これを労働者に周知させることも義務化されました。
詳しくは厚生労働省のパンフレット「職場における熱中症対策の強化について」や、リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」に記載されていますのでご参照ください。
(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
熱中症の労災事故の実例
熱中症の労災事故の実例を紹介します。
厚生労働省 職場のあんぜんサイト 労働災害事例集より
1 体育館新築工事現場において、土砂をスコップで集める作業をしていた作業者が熱射病により死亡した事例
昼休憩後の午後1時より、作業を再開し、被災者は土砂をスコップで集め、埋戻し作業を行っていた。午後3時頃、重機運転手は被災者がフラフラしていたため休憩するように指示したところ、被災者は日陰の方向に歩いていき倒れ込んだ。
なお、被災者は身体の具合が悪いということで災害発生前日まで約1か月間休業していた。
当日の天気は快晴であり、被災者の作業は、午前中からほとんど直射日光をさえぎるものがない場所で行われていた。気象台によると午後3時の時点での気象条件は、気温37.2℃、風速1.8m/S、湿度62%であった。
当該工事現場の休憩所として立ち上がった体育館を利用しており、そこに茶等が置かれていた。
(原因)
関係者の間で、炎天下での作業における熱中症の危険性についての認識がほとんどなかったことに根本原因がある。
飲料水のみならず、塩の備え置きがなかった点は、労働安全衛生規則617条違反であるし、適宜の休憩をとらせることが必要であった。また、被災者の健康状態を確認し、良好でなければ作業に従事させない、従事させたとしても作業中の健康状態の確認が必要であった。
2 産業廃棄物処理場で廃棄物仕分け作業中に熱中症で死亡した事例
災害発生当日、被災者は午前8時頃処理場に到着し、建設廃材の仕分けの方法、仕分けたものの集積場所等の説明を受け、ドラグ・ショベルで仕分けしやすいように掘り起こされたものの仕分け作業を開始した。
正午から1時間の休憩があったが、被災者は、処理場にあった空きドラム缶の中で自分で持参した「おむすび」一つと飲物を摂った。
午後1時から午前と同様の作業が進められたが、午後3時15分ころ、被災者はよろけて倒れ、手に軽い怪我を負った。
それを見た同僚が近くの日陰で少し休むように言ったところ、被災者は「気分が悪い」と言ってよろよろした感じで事務所の方に歩いて行ったが、まもなくその場にうずくまったまま動かなくなったので、近寄って声をかけたが返事をせず、また、飲物を与えても飲もうとしなかった。
そこで同僚は被災者を車に運び、クーラーをつけて寝かせたものの、回復の気配がないので病院に移送したが、当日の午後11時に死亡した。死因は熱中症であった。
(原因)
①暑熱下で長時間の作業を行ったこと
被災者が作業を行っていた場所には日陰がほとんどないにもかかわらず、適切な休憩の設備を設けず、また、このような職場環境と30度を超える炎天下の中で、熱中症予防のために適度の水分、塩分の摂取等をせずに作業を行った。
②直射日光下での服装が適切でなかったこと
内側にタオルを巻いたヘルメットの着用等、他の作業員の麦わら帽子と比較して日光の遮へい、放熱の面で必ずしも適切でなかった。
③体調が万全な状態ではなかったこと
被災者は、採用後5日目であるが採用に当って健康診断を行っておらず、また作業当日の体調の確認も行っていなかった。
3 道路清掃作業に従事していた作業員が熱中症にかかった事例
被災者は国道の清掃作業に従事しており、具体的には片側三車線道路の路側帯の清掃、フェンス内側雑草の除去であった。
被災者は午前9時から作業に取りかかった。午前10時に道路の下の日陰で約15分の休憩をとり、再び約45分の作業の後、日陰で15分の2度目の休憩をとった。正午から午後1時まで昼食と休憩をとった後、作業に戻った。
午後2時頃、被災者が座り込んだため、作業指揮者は被災者に日陰での休憩を指示して作業に戻った。しばらく経って様子を見に戻った作業指揮者が、被災者が座り込んだ場所から約80m離れた場所で倒れているのを発見した。
(原因)
①災害発生前日と当日は最高気温が36度を超えており、午後2時の気温は36.4度であり、舗装した路上では輻射熱により更に高い温度であったと推定されること
②被災者は経験年数は3年であるが、68歳と高齢であったこと
③健康診断が実施されておらず、被災者の健康状態、既往歴などが把握されていなかったこと
④被災者が気分が悪くなって休んだとき、顔色の確認と被災者との会話で、症状が軽いと判断したこと
熱中症との認識はなく、一人で休憩をとらせ、症状が悪化して病院に搬送した。
労災による熱中症の損害賠償請求について
勤務先会社(使用者)は労働者が就業するにあたって、その生命、身体、健康の安全に配慮する義務を負っています(労働契約法5条)。
熱中症のリスクの高い環境下で、適切な対策を取らずに就業させた結果として熱中症が発症したり、発症後の適切な対策をとっていなかったために重症化して死亡したり、後遺障害が残ってしまったという場合、勤務先会社(使用者)には安全配慮義務違反があるとして、損害賠償責任が認められることが多いと考えてよいです。
熱中症になり、症状がそこまで重くなければよいのですが、場合によっては、脳や臓器に後遺障害が残ってしまったり、最悪の場合は死亡することもあり得ます。
労災保険からは、治療費や休業補償などの給付はありますが、慰謝料は一切ありませんし、休業補償も給料全額までは補償されません。さらに後遺障害や死亡事故となった場合、将来得られたであろう稼働収入も全部はカバーされません
したがって、熱中症労災の労働者ご本人やご遺族は、労災保険からの補償給付の他に、勤務先会社(使用者)に対して、慰謝料や逸失利益等、労災保険ではカバーされない損害を賠償請求することによって確保することはとても大切なことです。
具体的に損害賠償請求として、具体的にどのような内容、金額の請求が可能なのかの目安については、次の記事をご覧ください。
労災でご家族を亡くされた方へ | 札幌の弁護士による労働災害相談(河口法律事務所)
早めの相談・依頼で安心を
ここまで過労死(脳・心臓疾患、精神疾患)と労災保険、損害賠償請求について、なるべく平易にご説明して参りましたが、やはり労災認定が実際にどのようになるのか、勤務先会社へはどのように請求すればよいのか等、法律の専門家ではないご本人、ご家族には難しい面も多々あると思います。
自分の主張は法律的に正しいのか、証拠資料の裏付は十分なのか、損害賠償の基準(相場)は合っているのか、他に請求できるものがあるのかないのか、裁判例などの実務上の取り扱いに沿っているのか否か・・・と不安点をあげればキリがないと思います。
そこで、経験豊富な弁護士に相談・依頼して、労災認定のサポートをしてもらうという選択肢があります。
また、勤務先会社に対する損害賠償請求についても、弁護士に依頼して、その可否の検討、賠償請求手続を行ってもらうという選択肢があります。
弁護士は損害賠償請求が可能と判断した場合、通常、いきなり裁判を起こすのではなく、会社に通知書等の書面で損害賠償の請求をして示談交渉を行います。残念ながら話し合いで解決できない場合(示談解決できない場合)には、その先のステップとして裁判解決を目指すことになります。
そのため、裁判まで行かずに示談交渉で最終解決に至る割合はかなり高いのです。
弁護士は、労災の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。